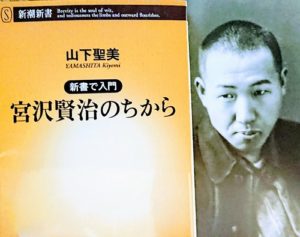すべてを飲み込み消化してしまう強靭な胃袋のような作品
『四谷怪談―悪意と笑い―』廣末保(岩波新書)

鶴屋南北の「東海道四谷怪談」に関するこの廣末保の著作は、同じく南北の「四谷怪談」に関する本(小林恭三)にも『格別な存在』『そのエネルギーと洞察の深さには畏敬の念を覚えます』と書かれてあることや、アンコール復刊したもののようでもあることから、どうやら「四谷怪談」に関する本としてはなかなかの名著らしいです。
しかし、それにもまして凄いなと思うのは元となっている南北の作品の力です。江戸時代のまだ劇作家とか作家とか、そんな言葉も生まれていない時代の歌舞伎のために書かれた「四谷怪談」。その研究本が新書という形式で数冊もあるというのは、他の文学作品をみまわしても、そう多くははなはいでしょう。それだけ研究者にとっては、非常に興味をそそられる作品であり、書くことも沢山ある要素を備えたものと言えるのだと思います。
この本から引用抜粋した気になる文章を記載したのですが、そこには「四谷怪談」を語るにあたり何度も本文中に出てくるキーワードがあります。
越境、グロテスク、無秩序、無媒介、悪意、悪、笑い、猥雑、ナンセンス、崩壊、…
といった言葉で、それらはすべてを飲み込んでしまうカオスそのものの混沌としたエネルギーを想像することができても、理路整然に整理されていく様子はイメージしづらいものがあります。
例えて言えば、あらゆる食べ物をごった煮状態で消化する胃袋の中のようなそんなイメージを私は想像します。ヤワな胃袋だと消化不良を起こして、吐き出すしかない、それらを受け入れるには丈夫で骨太な胃袋でなくてはありません。
鶴屋南北の「四谷怪談」は、そんなパワーを持っているとこの本を読んでそのような印象をもちました。
ちなみに、この廣末保の「四谷怪談」はそれが書かれた化政時代を崩壊の時代と、逆に小林恭三は近代の黎明期、人間性の解放とする立場で論じており、そのどちらににボクは共鳴するのか?すこし熟成の時間が必要かなと思いました。
“越境しあってはならないものが越境しあう。絶対に出会うはずのないもの同士が、おどけた仕種でそれぞれの秩序の外に踊り出して、出会う。無秩序を方法化した、滑稽でグロテスクな空間がそこに出現する。”
“異質なものが無媒介・非序列的に雑居しあっている不安定でグロテスクな空間の深さである。底が見えず、ただ亀裂を通して地の奥から哄笑だけが聞こえてくるような空間の深さである。”
“不条理に翻弄されて偽善化するほかない無力な善を声高にあざ笑う痙攣的な悪の魅力がある。南北は、伊右衛門の不義・背徳に悪の魅力を重ね、そうすることで崩壊期の悪意のエネルギーに形を与えようとしている。”
“いたるところに落差が生じる。そのため対象は多焦点的に拡散させられ、断片化する。そして物語の筋がその断片のあいだを縫って展開する。筋はこの場合、その拡散的な断片を、整序化された単一な集合体へと収斂していくような筋ではない。むしろ筋は、猥雑・無秩序な絵模様のなかに織り込まれていく。”
“それは笑う悪の笑いであった。だがそれは愁嘆も、殺しさえも、ナンセンス化してしまいそうだという意味においてもそうであった。また、様式も秩序もナンセンス化して猥雑な劇空間を作り出してしまうという意味においてもそうであった。”
“美しいだけの女形の幽霊は、加害者の悪と葛藤することができない。それができるためには、女形の幽霊も、悪や笑いと対抗できる幽霊に生まれ替わらねばならない。加害的な<悪>のエネルギーを発揮する幽霊に生まれ替わらねばならない。”
“鉄奬つけから髪梳きへと進行していく時間は、一切の日常的雑音を舎象しながら、集中的・求心的な劇空間を出現させていく時間であるはずであった。にもかかわらず南北は、その間に赤子の泣き声をからませることによって、猥雑な日常空間を割り込ませ、そうすることで、お岩の変身に二重の意味をもたせた。一つは、いうまでもなく「気をもみ死」しての変身であるが、いま一つは、拡散のなかにひそむ猥雑なエネルギーを背負っての変身であった。お岩の顔のグロテスクは、猥雑なエネルギーのもつグロテスクでもあった。崩壊期の悪意のエネルギーと拮抗しつつ、それを顔の形へと転換させたグロテスクでもあった。”
“歌舞伎的な発想による場面の作り方や役者の組み合わせやその登場のさせかたが、ある論理を、筋の必然によってではなく結果的に、発見してしまうというその関係がすこぶる興味深く思われる。”
“戸板に打ちつけられた死骸という、屈辱と醜悪の形をになったお岩の悪と、その悪に脅えながらも「業が尽きたら仏なれ」といい放つ岩 伊右衛門の悪が、川と土手のその境で、ほとんど重なり合うように対峙することによって、悪の美を競演する。崩壊期の悪意のエネルギーが、様式的ともいえる構図のなかで、悪の美として顕在化される。しかし様式的といっても、それはお岩の死骸のイメージであり、まさに崩壊のイメージでもある。”
“いつ恐怖が笑いに、笑いが恐怖に裏返るかもしれないような不気味さこそが、崩壊期の不気味さであり、そして面白さでもあった。ものみなが、それぞれの領域を越境して無秩序化してくる崩壊期の、それが矛盾であり、かつ可能性でもあった。”
“物語の結びとしては、伊右衛門は死んだと誰しもが思うだろう。だが、感覚的には、伊右衛門は死にきらないままの宙吊り状態でそこに止まっている。ということは、お岩もまた成仏しきれないままの宙吊り状態に止まっていることになる。”
“『四谷怪談』の悪や笑いや無秩序な劇空間のなかにひそんでいるエネルギーは、どこへどう製序的に統合され止揚されていくのか、それを『四谷怪談』そのもののなかで読みとることはできない。というよりも、『四谷怪談』はそうした志向を拒否した作品であった。崩壊期を千載一遇の好機とばかりに、無秩序の方法という逆説的な方法を手に入れ、そうすることで、崩壊期の拡散的なエネルギーに形を与えた作品であった。”
※引用『四谷怪談―悪意と笑い―』廣末保(岩波新書)