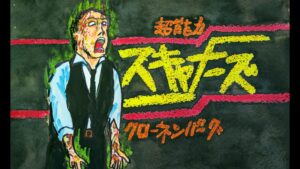幻想と欲望の「ビデオ・ドローム」

映画「ビデオ・ドローム」(1983年)
■監督:デヴィッド・クローネンバーグ
■出演:ジェームズ・ウッズ、デボラ・ハリー、他
デヴィッド・クローネンバーグ監督作品の「ビデオ・ドローム」は一番最初に見たときから、その印象がドンドン変化している作品で、その点において、私にとっては非常に特異な映画だと思います。そして公開から40年以上経った今、思うことは、これ凄い映画ということ。
最初に見たときはテレビの画面が変形するなどのビジュアル的な異様さに興味が注がれ、メディアからの影響を受けて幻想をみること、メディアの麻薬性って、あるのかなーと思っていましたが、この映画が公開された当時はレンタルビデオが出始めの頃で、インターネッㇳもスマホもなかった頃。しかし、その後メディアが発達し、状況が大きく変わってきた。今じゃ、猫の杓子もスマホを手にしてる。食事中だって手放せない。そしてスマホには興味ある情報が選別されて見ている者の手に届く。やがて頭の中が染まってくる。家族や夫婦の断絶が起きようとも・・・。
このビデオドロームは一種の深層心理ドラマ、主人公マックス・レンの心象風景を映像化したように思える。欲望が象徴となって表出する白日夢、夢の世界なのだ。そう考えたらなんてこの映画は先鋭的なんだろうと思う。お腹に女性性器のような裂け目ができて、そこにピストルを突っ込むのも、テレビの画面に囚われたデボラ・ハリーが映り鞭を打ってと懇願、レンがテレビに鞭を打ちつけも、いつのまにか違う女性だったというのも、すべては幻想なのだ。時代の影響を受けているので、今の映画に慣れている世代にとっては陳腐に映るかもしれないが、映像制作技術でCGがない時代に、こんな挑発的な映画を作ったとは驚きさえ感じる。
そうした無意識下の欲望の表現が、そもそも変だと思う人、私にはそんな趣味はないという人、笑うしかないという人など、映画を観て、もしそう感じさせたら、それはたぶん映画の勝利と言えるのだろう。ギリギリの線を走っているので、賛否はあって当然なのだ。
映画のオブリビオンというテレビにしか登場してこない学者は、マーシャル・マクルーハンがモデルと言われている。メデア論においては欠かすことのできないマクルーハンの有名な言葉。
メディアはメッセージである。
コンテンツではなく、メディアこそが人々の生活に変容をもたらすということ。 人間の拡張としてのメディアは、人間の感覚に反作用して新しい経験、関係性の形式を生み出す。メディアのメッセージを受け、いつしか、それを手放せなくメディア虜になってしまう。ビデオ・ドロームによって脳に腫瘍ができてしまうと映画にあったが、それもまんざらではないかもしれない気がする。
「ビデオ・ドローム」は古くて、新しいのだ。我々はこの世界のすべてを見ているわけではない。我々は片寄った世界の中で自分の都合のいいように世界を各々、構築している。だからどこからが現実で、どこまでが幻想なのか、あるいは虚像なのか?それさえも怪しい感じと言えないだろうか?
我々は見ている世界を、実は、現実と幻想、虚像を、欲望のファイルターをかけ、混同し、錯綜させているのではないか。そんなことを感じさせるのが「ビデオ・ドローム」だ。そして最終的に自我が崩壊するのを描いているのでは?と。
私にとっては、この映画は、大傑作ではないかと思いはじめ、ここへきて急上昇してきたのだ。