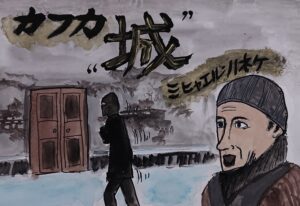カフカ、心理世界の迷宮と悪夢の渦の中で・・・

「KAFKA 迷宮の悪夢」(1991年)
■製作年:1991年
■監督:スティーヴン・ソダーバーグ
■出演:ジェレミー・アイアンズ、テレサ・ラッセル、アレック・ギネス、イアン・ホルム、他
今や巨匠となったスティーヴン・ソダーバーグ監督の長編第2作目、『KAFKA 迷宮の悪夢』。1990年初頭の公開当時、劇場で鑑賞したものの、記憶に残っていたのはモノクロの映像と重厚なヨーロッパの街並み程度で、話の筋は忘却の彼方。ソダーバーグ監督の映画は一目を置く作品が多く、才能煌めく若き彼が、カフカを、どうとらえ映像化したのか注目する部分もあった。
物語は1919年のプラハを舞台に、昼は保険会社で働き、夜は小説を書く作家カフカが、友人の溺死事件をきっかけに不可解な出来事へ巻き込まれていく。彼は調査の中でアナーキストたちと出会い、それを追うカフカが、事件の鍵を握るムルナウ博士とカフカの小説にもなっている「城」にたどり着くのだが、そこで明かされるのは恐るべき実験の数々。映像は「城」「権力機構」「官僚主義」といったカフカ文学特有の文学モチーフが巧みに織り込まれ、次第に悪夢のような世界へと引き込んでいくわけですが、こうした展開にソダーバーグの才能のきらめきを感じなくもない。
ムルナウ博士の名前でわかるように、この映画はあきらかに1920年代のドイツ表現主義と呼ばれた映画の、幻想的映像世界の再現をどこかで意識したといえるだろう。そして、リスペクトさえ感じるのが、同じくカフカを題材にしたオーソン・ウェルズ監督の「審判」だろう。モノクロで捉えた陰鬱なプラハの街並みや、不安を誘う光と影のコントラストは、それを表していると思う。
しかし、ここでソダーバーグは彼なりの味付けをしている。キーとなる「城」の内部に足を踏み入れたとたんに、画面は突如としてカラーに変わり、視覚に鮮烈な変化を与える。さらにムルナウ博士の人間を家畜化させるための異常な実験のための巨大装置は、舞台となった1919年という時代を飛び越えて、近未来的でSF映画の要素も加わってくる。カフカの小説は、不条理な人間心理と権力機構、官僚主義の不安さを連想させるゆえ、そのイメージを飛翔させると、それは未来的なものに近づくのだ。その意味でもカフカの小説はとても現代的と言えるのだ。
興味深いのは、こうした不安感や不条理さが漂う一方で、作品全体に流れる遊び心だ。カフカの名前や文学的枠組みから深刻さを期待しがちだが、まるでカフカの世界観を発想の手がかりとした一種のゲームのようで、そこに深刻なテーマを探す必要はない。これは悪夢ではなく、ゲームなのだ。そう視点を切り替えることで、映画は意外なほど楽しめる作品へと姿を変える。
この作品の前作、『セックスと嘘とビデオテープ』でカンヌ国際映画祭において最年少でグランプリに輝いたソダーバーグ監督。2作目にしてまるでカメレオンのごとき変貌を見せ、別人のような演出スタイルを披露した点は驚くべき才能と思った。
カフカを素材としたこの作品は、悪夢という枠組みを超えて、まるで遊び心に満ちた迷宮といえそうだ。30年前に映画館で観たときは、気づかなかったソダーバーグの才能のきらめきを感じたとともに、はカフカという難解な題材を、映画ならではの手法で独自の世界を創り出したのである。