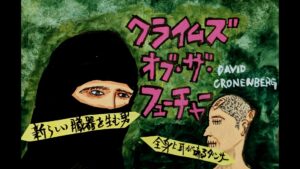愛とエゴの狭間で破滅する男女「イングリッシュ・ペイシェント」

映画「イングリッシュ・ペイシェント」(1996年)
■監督:アンソニー・ミンゲラ
■主演:レイフ・ファインズ、クリスティン・スコット=トマス、他
映画「イングリッシュ・ペイシェント」は、1996年に公開された映画で、マイケル・オンダーチェの小説を、アンソニー・ミンゲラ監督が映画化しました。
第二次世界大戦末期のイタリアとアフリカを舞台に、全身やけどした重傷の“英語を話す患者”をめぐる過去と現在が交錯する物語です。ある意味で、愛によって破滅してしまうのですが、私には恋愛ロマンスというよりは、特権階級の主人公が恋愛に溺れ破滅した物語に映りました。
この『イングリッシュ・ペイシェント』は、当時アカデミー賞を総なめしたので、私もタイトルが記憶にのこっていたのですが、果たしてそれにふさわしい作品だったのか、ちょっと疑問視したくなる部分もあります。
壮大でロマンチックな戦争ドラマではあるのですが、映像が素晴らしく美しいし、これぞ映画という画面だったのですが、特権階級が自由に遊んだ結果が、悲劇的結末を迎えたというふうにどうしても見えてしまい残念な気がします。
主人公やヒロインの痛みや悲しみというのがあまりつたわっつてこない。むしり、あっつけなく描かれていた周辺の人々の痛みのほうが感じられました。浮気された旦那が嫉妬で心中をはかり、彼は砂漠のど真ん中で葬られることなく死んでいった。でもそもそもの原因を作ったのは誰?となってしまい。これじゃ、旦那が浮かばれないな、かわいそうだなと。
「ハートは炎と燃える器官だから」とセリフにありましたが、それはわかります。人生、いろいろあるから、それは否定しません、それを否定したら映画なんてできません。自らのエゴにより自らが破滅するのは、美学もありいいのですが、周囲を巻き込んで破滅させてしまうのはつらいという気持ちが残ります。
そこで思いました。映画と言うのは、どこか夢を見ているような部分もありので、特にこうした大河のような話は、主人公をどこか等身大、身近に感じる部分を描きながら、エゴだけでは、共感しづらいのだなと。