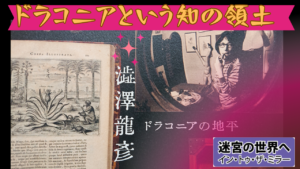澁澤さんの映画論「スクリーンの夢魔」

希代の知識人であった澁澤龍彦。その彼が映画について書いた文章をまとめた本が、『スクリーンの夢魔』。そこに言及されている映画は、当然、執筆した時代背景があり、古い作品が多い。なので読み手側のイマジネーションを掻き立てながら読んでいくということになります。
ちなみに、見たことがない映画について書かれたものを、その修飾された言葉から、どんなにかすごいのだろうと想像が掻き立てられたりすることがあります。その映画は見てもいないのに、作品が神話的な存在へと持ち上げてしまうこともあります。つまり映画が勝手に一人歩きを始めるのです。そうしたことは、映画に限らず文学でもスポーツでもあることだとも言えます。伝説の試合とか。それは今のように、情報が氾濫し、簡単に映像としてみることができる時代とは違い、書かれた文字から想像するわけですから、イマジネーションの環は膨らみ、想いや憧れも強くなろうというもの。
ところで、澁澤の映画に関する文章を読んでいると、映画そのものに触れているのは全体の半分くらいではないか?ということに気づきます。主題に入るまでの前書きが、長いのです。前段部分で澁澤の世界をまず構築し、そこから肝心の映画の話題へと進むパターンが多い。取り上げる映画のテーマに関連する周辺の歴史、思想、事象などがさりげなく書かれているのですが、そこが澁澤の凄さが光っているところなのです。それを知っているかどうかで、映画の楽しみ方も違ってくる。
例えば、古い話なんですが、ホラー映画ブームのきっかけともなった「エクソシスト」(1973年)という有名な作品があります。そについて書かれたものを見ると関連事項として、ポルターガイストについて言及しています。霊の力によって家具などのモノなどが動いたりする現象を指すのですが、後年、「ポルターガイスト」(1982年)という映画が登場しヒットすることになるのですが、それを予言していたかのようです。時代を経て読むと、澁澤の知の胆力に驚かされるのですが、澁澤さんは、日常生活においてテレビのスイッチの入れ方を知らないと書いている(当時はリモコンなんてない時代です)。おかしな人、不思議な人。今のAIについて、彼はどう感じるのでしょうか?
この本では様々な映画、監督が紹介されていますが、ルイス・ブニュエル、イングマール・ベルイマン、ルキノ・ビスコンティ、ルイ・マルらを評価しているようでした。また怪奇モノに興味があるらしくそのジャンルの映画の紹介も多い。ちなみにお気に入りの女優は、カトリーヌ・ドヌーヴらしく、彼女への言及部分は澁澤のエロスの女神としかいいようがないほど。ところで、マルキ・ド・サドを紹介し、ワイセツ裁判まで起こした澁澤は、そのカトリーヌ・ドヌーヴが主演し、ロジャ・ヴァディムが監督した映画「悪徳の栄え」についても言及しており、彼女への言葉はさておき、作品論的には手厳しい評論を下しています。それを読む限り澁澤は、作品としての価値、観念の理想、具現化求めた作家であったのだとあらためて思うのでありました。
最後に、澁澤が映画について語るとき良くも悪くも、フロイトの精神分析論との関連性についての事項が多いことに同時に気づくのですが、それからは、フロイトの理論を導入してみてみることが、この本が書かれたころの知識人の映画の見方の、ひとつの方法論であったろうことがわかろうというものです。私も、思い返せば、そうしたものの見方に影響されフロイトの「夢判断」などを読んだ記憶があります。今ではそうした文章自体を見ることも珍しくなっているのではないでしょうか。時代ですね。
◆澁澤語録◆
そもそもユートピアとは、歴史のパースペクティヴを見通そうとする私たちの眼が、そのような連続性の断ち切れたところに生じせしめる、一種の幻想ではなかったろうか。見通すことができないからこそ、ユートピアの幻想、あるいは、逆ユートピアの幻像を見るのである。ユートピアとか逆ユートピアとかいった区別をつけること自体、すでに私たちが、現在の私たちの価値基準にとらわれていることの証拠なのであって、あえていえば、あらゆるユートピアには価値はなく、ユートピアと逆ユートピアとは結局、同じものの別名にすぎないのである。
あえて極言するならば、文化も宗教も、狂気も夢も、すべて人間の不安のとうえいでしかなく、恐怖による虚無からの創造物だと称することができよう。恐怖こそ、すべての人間の人間の上部構造の原因なのである。いわゆる下部構造と見なされた社会の経済的機構も、この恐怖の一様態と考えて差支えあるまい。自己保存の本能は、恐怖なしには考えられないからだ。いわば恐怖の土台の上に、人間は空中楼閣のごときイデオロギーの花々を咲かせたのである。
※『スクリーンの夢魔』澁澤龍彦から引用