すべてを知っていることは、何も知らないことと同じ・・・
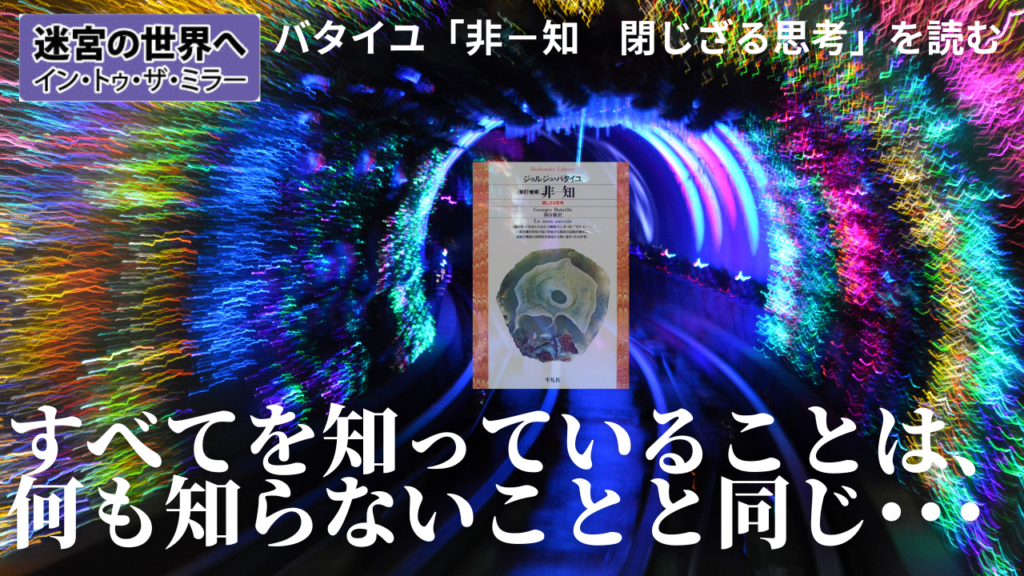
『非-知 閉じざる思考』 ジュルジュ・バタイユ (平凡社ライブラリー)
ジョルジュ・バタイユの「非-知 閉じざる思考」は、彼がテーマとした<非-知>について講演であったり草稿であったりをまとめたもの。ただ、この<非-知>がやっかいで、バタイユによると理性ではわかり得ない領域をさしており、ある究極の状態であるということなのである。さらに<非-知>を説明不能の状態を指しているものの、それを伝えるため言葉で語っているため二重性が発生しているのです。
読んでいると、きっとバタイユこのようなことを言っているのだろうと憶測するものの、もともと言語化できないもののためその憶測やイメージは実際それでいいのか確かではありません。そこで、本の巻末に収録されている解説を読むと、このバタイユの本を訳した西谷修氏の文章がわかりやすいということに気がつきます。バタイユの断片的な思想表現は彼の解説によってよりわかりやすくなっていると感じました。そこで西谷修の解説の一部を引用し下記に記すこととしました。
↓ ↓ ↓
“非-知をテーマ化するとはどういうことなのか。それを検討するには、当然ながらまず「内的体験」に立ち戻らなければならない。というのも、バタイユによれば非-知とは、内的体験の極点における主体のありようとされるからだ。
バタイユのあらゆる思考の運動のアルファでありオメガである「内的体験」とは、かつては宗教的伝統のなかで神秘家と呼ばれた人びとが生きた、信仰の極限体験に等しいものだと言ってよいだろう。ただし、それが「等しい」と言いうるのは、「内的体験」の立場から見たときだけである。というのも、神秘体験は何らかの教義にもとづく信仰を前提にしており、それゆえに救済の価値をもつものだが、バタイユはむしろ救済の願望を隷属として斥け、いっさいの教義的前提を排して「極点」を追求しようとするからである。
だからキリスト者や神秘主義の立場からは、バタイユの考えは認めがたいものとなるが、バタイユの方は自分を「神秘家たちの衣鉢を継ぐもの」として位置づける。バタイユはこのエクスターズ(脱存)の瞬間を、神の権威や信仰に帰するよりも、むしろ世俗的な意識の経験のうちで生きようとした。それはどうでもよいものにしてしまうものだったからだ。ところが宗教的な教義の枠組みなしに、このような自我の意識を喪失(離脱)する「体験」が、何らかの「極点」として生きられたことはなかったし、それが論理の言葉で明確に記述されたこともなかった。
だからバタイユはまずこの意味づけられない「体験」が何であるのかを、まったくの闇のなかで手探りしなければならなかった。というより、何であるかもわからないままで、それは鬱病の発作とも区別されない病的な精神の変調でしかなかったのである。
そしてバタイユにこの体験が何でありうるかを、ほとんど啓示のようにして悟らせたのが、アレクサンドル・コジューヴの『精神現象学』講義を通じて理解したヘーゲルの哲学だった。「意識の経験の学」と副題されたこの書物は、主体としての理性が世界の対象化によって知として自己を具体化し全体化してゆく過程として記述されており、理性の究極的自己実現としての絶対知は、原理的には把握され言説化された全現実=全理性だということになっている。
バタイユはその絶対知に、一般的な知の経験との関係でおのれの体験の位置するところを見定めたのである。絶対知はみずからの可能性をくまなく実現した理性として、知となりうる全現実をすべてその内部に抱えているが、そのように実現された内在的全体は、それ自体もはや何ものにも支えられることなく虚空に浮かぶことになる。
言いかえれば、知の内部にとどまるかぎり、そこではすべてのものがくまなく意味づけられているが、知られたものの全体はもはや何ものにも関連づけられず、意味がないことになる。その事態への覚醒は、全体的知を深淵にさらし、それまで意識を導いてきた知的体験を、めくるめく闇への失墜の感性的強度の体験へと転化する。すべてを知っているということは、とりもなおさず何も知らないのと同じことなのだ―その覚醒が非-知なのである。
そして「極点」がこの意味での非-知でありうるという確信によって、信仰なしの「体験」ははじめて一般的な知との関係で論理的に構成しうるものになる。極点そのものが記述不能の瞬間だとしても、それを知の経験の限界に位置させてくれることはできる。バタイユが内的体験をそのような極点として「可能事の果て」として生き、一般的な認識の運動との関係で、それを意味の崩壊する瞬間として記述しうるようになるのもこのときからである。
「・・・・・・わたしにはヘーゲルがどうしても必要だった。ヘーゲルがいなければ私がヘーゲルにならなければならなかった」(『有罪者』)というのは、このような意味で言われている。つまりバタイユがそれまで名づけることもできず、明言することもできなかった「体験」を、はっきりと打ち出すことができるようになるためには、その自我の喪失の瞬間を非-知として位置づけることが必要だったのであり、その「自覚」によってかれは内的体験を語りうるようになったのである。
だから非-知に関して確認しておくべきことがある。それはこの用語が絶対知との関連で用いられたものであり、絶対知がヘーゲル固有の用語であるように、非-知とはバタイユに固有な用語だということである。プロティノス以来、神秘主義の伝統のなかに「神的な無知」といった表現はあっても、「非-知」という言い方が用語として用いられた例は見当たらない。それは非-知が、たんに信仰と教義を排除しているからというだけでなく、ヘーゲルの絶対知以後に、その不可能性を画するものとして作られた言葉だからであり、内的体験にいかなる「神秘」もないように、非-知はあくまで現代の非宗教的な概念なのである。
おそらく『内的体験』においてもっとも理解されなかったのはそのことである。バタイユの「体験」はこの絶対知との出会いによって、みずからを非-知として見いだすことではじめて「内的体験」として記述しうるようになった。”
“”部分、ジュルジュ・バタイユ「非-知 閉じざる思考」(平凡社ライブラリー)所収の「訳者解説」西谷修から引用



