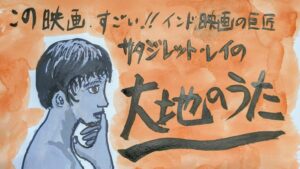母と子のすれ違う物語「大河のうた」
映画「大河のうた」(1956年)
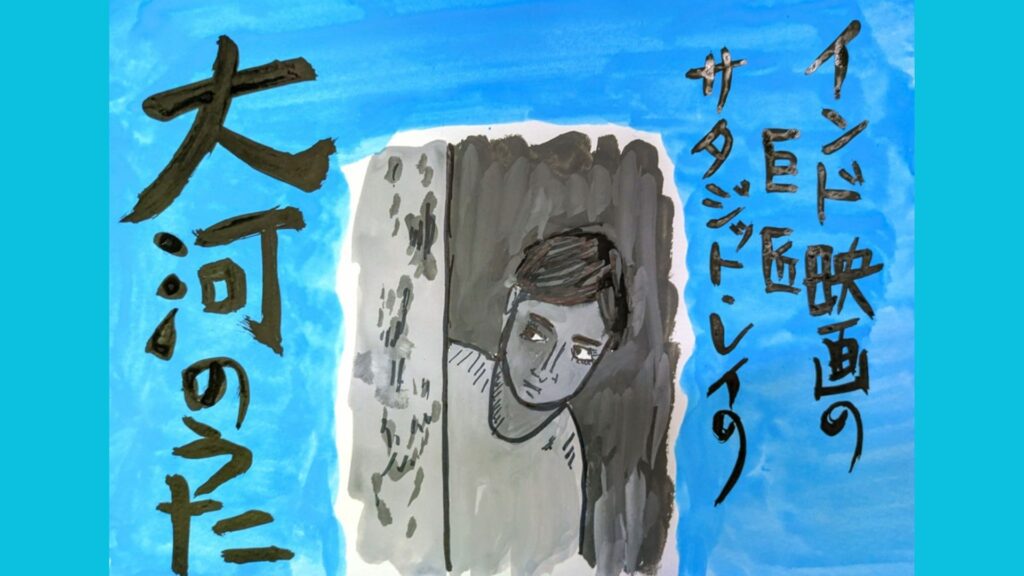
■監督:サタジット・レイ
■出演:ピナキ・セン・グプタ、スマラン・ゴシャール、カヌ・バナールジ、他
サタジット・レイ監督の『大地のうた』が、すごくよくて感動したので、その後の家族はどうなっていくんだろうと、興味が湧き『大河のうた』を見ました。この作品も、またとても深く深く描いており、感動を得ました。
田舎を離れた家族、しかし、そこで父親が死んでしまいます。父が聖なる水を飲みたいとガンジスの水を汲んできてのみますが、衛生面でどうなんだろうと思ったのですが、昔の人は免疫強かったのですかね。そうしたこともあろ、暮らしは全然楽になりません。相変わらずのわんぱく少年オプーは、同年代の子供たちが、楽しそうに学校に行くのを物陰から見て、母親に僕も学校に行きたいといいます。母親はお金がかかるね、とオプーに言いますが、学校にいけたので何とか行かせてあげられたのでしょう。
やがてオプーは大きくなり、成績も優秀で校長からカルカッタの大学に進学するよう勧められます。地球儀をわたされ、世界は広いということを知り、若いオプーは進学を希望するも、母親にそれを話すと反対され、オプーをプイと家を出てしまいます。そのあとを母親が追っかけて、悪かったカルカッタに行っていいと、ひそかにためていたお金をオプーに渡します。子供の未来のため、母の愛を感じさせます。見送る母の姿が切ない。
オプーは印刷会社で住み込み、昼間は学校、夜は仕事の二重生活。母親は田舎で孤独に暮らしています。当然ですが、母と息子がそれぞれ異なる道を歩むという、母子の避けがたい運命。そうした一つ一つが余白を残す演出で、味わい深いのです。
母にとって息子は生きる唯一の希望であり、日々の苦労を耐え忍ぶ支えそのものであった。娘を失い、夫を失い、貧しく社会的にも孤立しがちな女性にとって、息子の存在は、大きなの意味を持つ。しかし、オプーは成長とともに知識を求め、都会へと引き寄せられていく。若さの象徴です。教育の機会は彼の未来を開く希望であると同時に、母から彼を奪っていく側面を持っています。
母親からすれば、オプーが立派に成長することを望みつつも、病気がちになり、気弱になり、自分のそばにいてほしいとどかで願っている。息子のために自分を犠牲にする母でありながら、同時に孤独という感情を抱いている。思えば母は「大地のうた」から貧しさ、家事、世間の目と戦っていました。
一方、息子オプーは、田舎から都会に出てきて学問を学び、未来をみている。この年頃の男性であれば、あたりまえのことだろう。母の暮らす田舎に帰省しても刺激がなくおもしろくないと感じてしまう。親との距離が生まれてくるのだ。
オプーは母を裏切ろうとしたわけではなく、ただ自分の人生を歩もうとしたにすぎない。が、その選択が、母の孤独を決定づけることになる。こうしたことは、誰もが避けて通れない普遍的な出来事と言えるだろう。子どもは成長とともに親から離れていく、親はその喪失を引き受けなければならない。そして母の死・・・。レイはそうした人間が生きるうえでの普遍性を、きわめて繊細に、かつ詩的に描き出した。よくある話とも言えばそうで、さらにインドという他国の地の物語なんだけど、人間の生きていくことの避けられない普遍性をレイは描いており、胸に響くのです。そしてなによりもレイの演出が、すばらしく際立っていて時代を超える作品となっているのである。