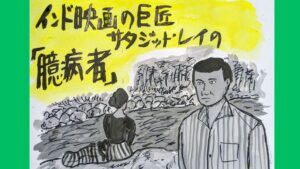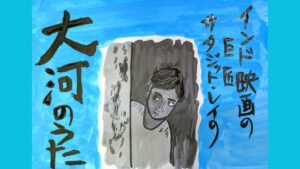深い感動が!インドの古典映画「大地のうた」
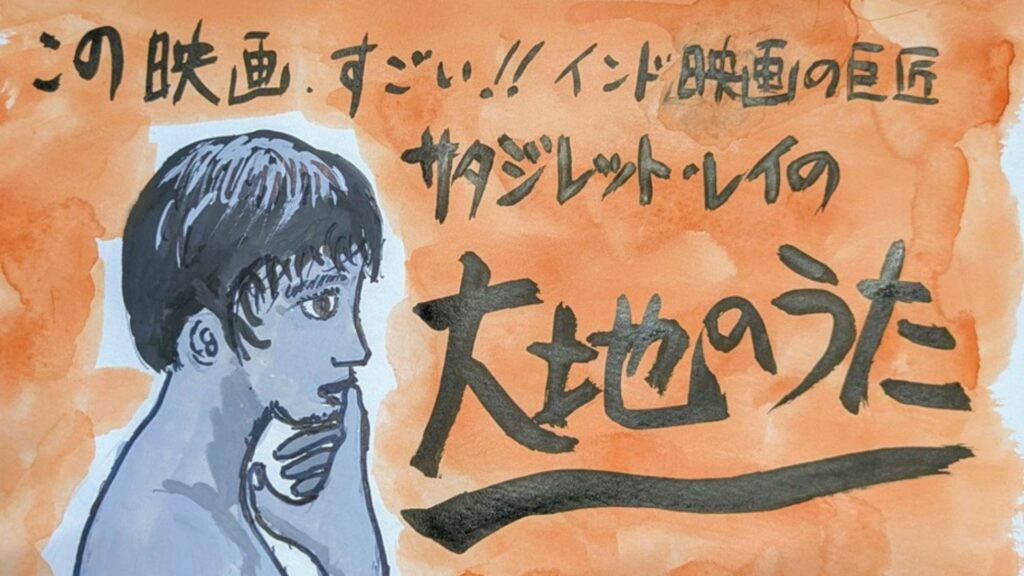
映画「大地のうた」(1955年)
■監督:サタジット・レイ
■出演:バナールジ、グブタ、カヌ・バナールジ、他
インド映画の巨匠として知られるサタジット・レイ監督。1955年に作られた「大地のうた」は映画史に輝く作品として知られています。映画を観始めてから、その作品の名を知っていても、長い間、観ようとあまり思いませんでしたし、見る機会もありませんでした。が、レイ監督の他の映画を観ているので、この映画を観てみようと思い立ち、観てみたのですが、これが、とても驚きびっくりしました。衝撃的でした。こんなすごい映画だったんだ!と・・・・。
インドのベンガルの村に生きる貧しい一家の日常を丹念に追った物語だったのですが、この作品がサタジレット・レイ監督のデビュー作とは思えないほど、豊穣な作品でした。この映画、レイが広告会社で働くかたわら、未経験のスタッフらとともに3年の月日をかけて作ったと言います。いわば映画づくりは、未経験ということですよね。信じられません。
映画は、貧しいゆえに生活に疲れている母、娘のドゥルガ、その弟のアプを中心に、そこに居候する老いたおばあさんを中心に何気ない日常を、日々の暮らしに苦労しながら、もがいて生きている様子を描いているのですが、カメラがとらえている映像、様子がどれも素晴らしいのです。映画にありがちな、大きな事件を描くわけではありません。日常に起こる困ったこと、うれしいこと、親しきものの死などがたんたんと描かれています。それだけで2時間魅せるわけですから、どれだけこの映画がすごいんだろうと思います。彼らは裸足だし、まさに着の身着のまま。子供たちが汽車を見るシーンがあるのですが、そんな近代の機械仕掛けの車を見るのは、生まれて初めての経験。
子供、ドゥルガやアプの一瞬一瞬の表情やしぐさが、まばゆいばかりに素晴らしく、胸に深く刻まれるのです。それらの映像はモノクロ映像で古い映像のため、決してクリアではありませんが、そうしたことを気にさせないほど、リアル感や映画的詩情を醸し出していきます。そして、終盤に訪れる姉ドゥルガ の死の場面は、いろいろな意味を含んでいるし、とても悲しいし、不条理だし、これからこの家族は、どうなっていくんだろうと思ってしまいます。それが三部作といわれるものにつながっていくんだろうなと思いました。
最初は、画面もモノクロで粗いし、テンポもスローで、劇的な展開もないので、観るのに少し戸惑うかもしれませんが、見続けるとだんだん映画の持つ世界に引き込まれていきます。見終わったあとは、何とも言えない深い感動が残り、まさに奇跡のような映画だなと思いました。「大地のうた」は、いまから70年も前の映画ですが、決して古びてはいません。私たちからすれば、経済大国として豊かになり、ネットなどにより情報過多の社会に身を置き、先進国でございとエラソーにしていても、何かが欠落しているし、根源的なものを映し出すからこそ、この映画の静謐さや素朴さが新鮮に、魅力的に響くのだと思います。
「大地のうた」は、現代では古典とよばれる部類の作品ですが、この作品の持つ魅力は時代を超えて語り継がれるのではないでしょうか?まさに人類史の遺産とでも言うべき作品です。こんなすごい作品だったとは今まで知りませんでしたし、名画を届けてきた岩波ホールのきっかけにもなったというのも頷けます。ベタ褒めですよね。そのくらいすごい映画でした。